祝日と祭日の違いとは?由来,旗日の意味,日数をわかりやすく解説【2026年祝日一覧付き】
もうすぐ2025年11月3日の「文化の日」。
ニュースやカレンダーでもよく見かける“祝日”という言葉ですが、ふと「祝日と祭日の違いって何だろう?」と思ったことはありませんか?
かつて日本には「祭日(さいじつ)」という言葉があり、皇室の行事を行う特別な日を指していました。
一方、現在私たちが使う「祝日」は、「国民の祝日に関する法律」に基づいて決められた国民全体でお祝いする日のこと。
実は意味も由来もまったく違うんです。
この記事では、
- 祝日と祭日の違い
- それぞれの由来や歴史的背景
- 「旗日(はたび)」の意味
- そして2026年の祝日一覧カレンダー
をわかりやすくまとめました。
11月3日の文化の日に合わせて、「祝日ってなんだろう?」を一緒におさらいしてみましょう。

文化の日に合わせて、“祝日”の本当の意味を知っておきたいね!
祝日と祭日の違いとは?
「祝日」と「祭日」は似ているようで、実はまったく意味が異なります。
現在、日本で使われている「祝日」は「国民の祝日に関する法律」で定められた日で、「国民がこぞって祝い、感謝する日」として制定されています。
たとえば「建国記念の日」や「文化の日」などがこれにあたります。
一方、「祭日」は昭和23年(1948年)まで使われていた言葉で、もともとは皇室の祭祀(さいし)行事を行う日を指していました。
「紀元節」「天長節」「新嘗祭(にいなめさい)」など、国の儀式と深く関わる日が多かったのです。
戦後の新しい憲法とともに、「祝日」として国民全体で共有する形に変わり、「祭日」という制度は廃止されました。
つまり、「祝日=国民が祝う日」、「祭日=皇室の行事日」というのが大きな違いです。
現在は公的には「祝日」のみが使われており、「祝祭日」という表現は“慣用的な言い回し”として残っているだけなんです。

“祝祭日”って言葉、今は正式には“祝日”だけなんだね!
旗日(はたび)とは?意味と由来をわかりやすく
ニュースやカレンダーで「旗日(はたび)」という言葉を見かけることがありますよね。
これは、国旗を掲げることが定められている日=祝日を意味します。
つまり、祝日はすべて旗日でもあり、自宅や公共施設に日の丸を掲げてお祝いする日なのです。
この習慣のもとは、明治時代にまでさかのぼります。
当時は皇室行事(祭日)や国家的な儀式の日に国旗を掲げてお祝いしていました。
その後、戦後の新しい祝日制度ができた際に、「国民の祝日」も国旗を掲げる日として引き継がれ、現在に至っています。
ちなみに、国旗の掲揚は義務ではなく“任意”。
玄関先やベランダなどに掲げるご家庭もありますが、最近はあまり見かけなくなりました。
ただ、官公庁や学校などでは今もきちんと掲揚されています。
「旗日」という言葉には、“国全体でお祝いする日”という意味が込められており、まさに祝日の象徴的な呼び名といえるでしょう。

祝日=旗日!つまり“お祝いの気持ちを国旗で表す日”なんだね!
2026年の祝日一覧と日数
2026年は祝日が16日、加えて振替休日が1日(5/6)、国民の休日が1日(9/22)発生します。
つまり公的な「休み」は合計18日になります(祝日16+休日2)。
2026年 祝日カレンダー(一覧)
※「休日」は振替休日・国民の休日を指します。
| 日付 | 名称 | メモ |
|---|---|---|
| 1/1(木) | 元日 | |
| 1/12(月) | 成人の日 | 1月第2月曜 |
| 2/11(水) | 建国記念の日 | |
| 2/23(月) | 天皇誕生日 | |
| 3/20(金) | 春分の日 | |
| 4/29(水) | 昭和の日 | |
| 5/3(日) | 憲法記念日 | |
| 5/4(月) | みどりの日 | |
| 5/5(火) | こどもの日 | |
| 5/6(水) | 休日 | 振替休日(5/3ぶん) |
| 7/20(月) | 海の日 | 7月第3月曜 |
| 8/11(火) | 山の日 | |
| 9/21(月) | 敬老の日 | 9月第3月曜 |
| 9/22(火) | 休日 | 国民の休日(挟まれ日) |
| 9/23(水) | 秋分の日 | |
| 10/12(月) | スポーツの日 | 10月第2月曜 |
| 11/3(火) | 文化の日 | |
| 11/23(月) | 勤労感謝の日 |
- 5/6(水)は、5/3(憲法記念日)が日曜のための振替休日です(祝日法第3条第2項)。
- 9/22(火)は、敬老の日(9/21)と秋分の日(9/23)に挟まれたため国民の休日になります(祝日法第3条第3項)。この結果、9/21–23が3連休、さらに9/19(土)〜9/23(水)で最長5連休(いわゆる“シルバーウィーク”)に。
参考:祝日は法律上年16日。これに加えて「振替休日・国民の休日」の仕組みで休みが増える年があります。

2026年は“敬老の日→国民の休日→秋分の日”で秋に連休が増えるよ。旅行やイベント計画は早めに!
振替休日・国民の休日のルールをわかりやすく解説
祝日が重なったときや、祝日に挟まれた平日が休みになる「振替休日」「国民の休日」。
聞いたことはあっても、仕組みまでは意外と知られていないですよね。
振替休日とは
祝日が日曜日と重なった場合に、翌平日を休みにする制度です。
たとえば2026年の「憲法記念日(5月3日・日曜)」がこれにあたり、翌5月6日(水)が振替休日になります。
これは「国民の祝日に関する法律」第3条第2項で定められています。
💡ポイント
祝日が土曜日に重なった場合は振替にならない点に注意!
国民の休日とは
祝日と祝日に挟まれた平日を自動的に休日とする制度です。
2026年では「敬老の日(9月21日)」と「秋分の日(9月23日)」に挟まれた9月22日(火)が国民の休日になります。
このルールによって、秋には“シルバーウィーク”と呼ばれる長い連休が誕生します。
この制度は、家族や友人と過ごす時間を増やし、国民全体でリフレッシュすることを目的として作られました。
祝日の並び方次第で連休が生まれるため、毎年少しずつ違うのも面白いところですね。

振替休日と国民の休日って、法律でちゃんと決まってるんだね!
まとめ|祝日と祭日の違いを知ると1年がもっと楽しくなる
「祝日」と「祭日」は似ているようで、まったく違う意味を持つ言葉です。
祝日は国民みんなでお祝いする日、祭日はかつて皇室の行事を行う日でした。
そして現在は「祝日」が正式な名称として使われ、「旗日」はその祝日に国旗を掲げる日を表しています。
また、祝日が重なったり挟まれたりすると「振替休日」「国民の休日」が発生し、自然と連休が生まれる仕組みになっています。
こうしたルールを知っておくと、1年のカレンダーを見るのがぐっと楽しくなりますよね。
2026年は秋に“シルバーウィーク”があるほか、春や夏にも3連休が多い当たり年。
旅行やイベント、家族の予定を立てるときは、ぜひ祝日カレンダーを活用してみてください。
きっと毎日の暮らしが少し豊かになります。

祝日の意味を知ると、ただの“休み”じゃなくて“感謝やお祝いの日”に感じられるね!
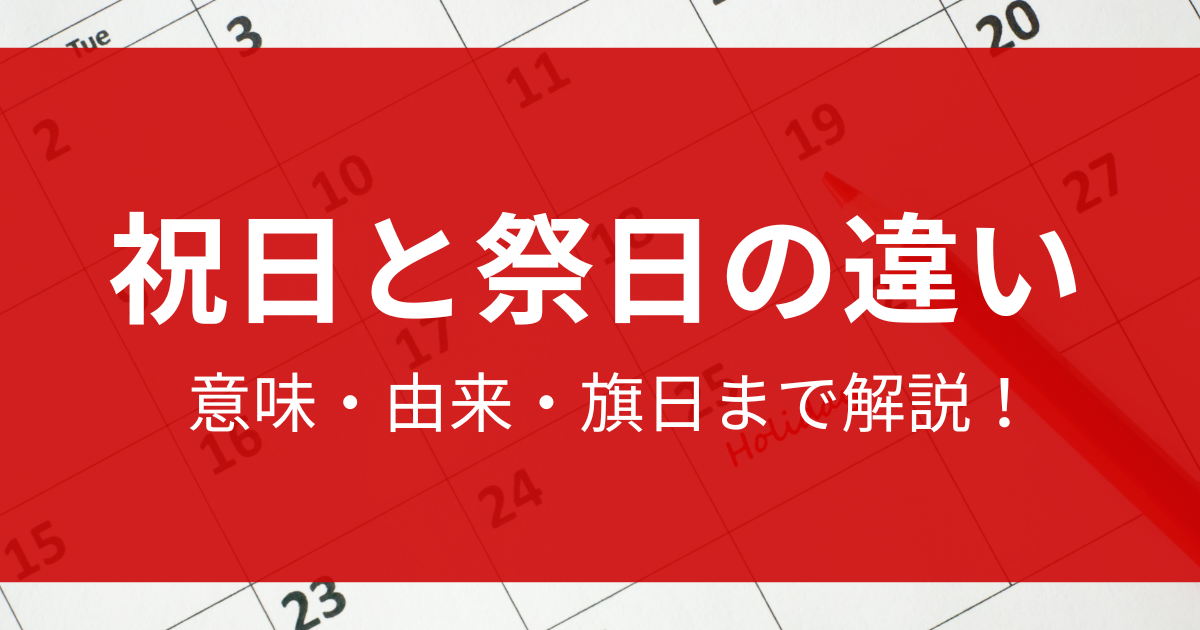
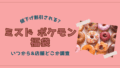
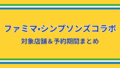
コメント